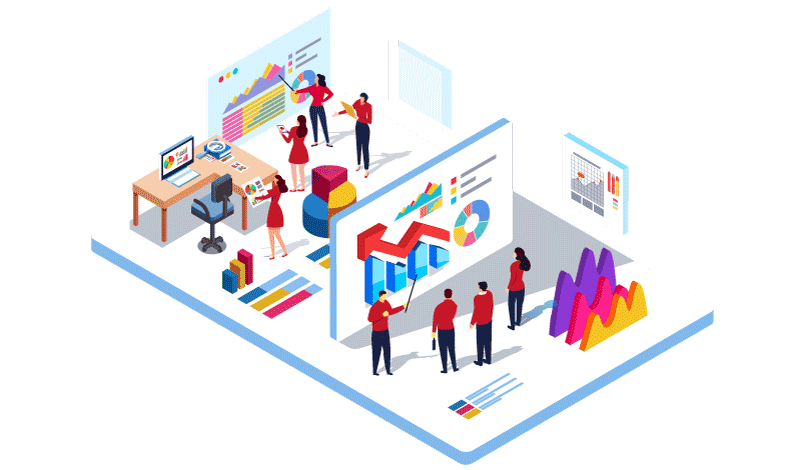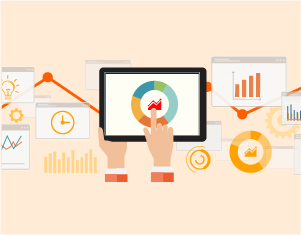-
コラム
2020/12/04
「価格」のメンテナンスを! 保守の大切さ
Tweet「適正価格」維持管理の難しさ
資産のメンテナンス・保守 実行できていますか?
一般常識になっているソフトウェア、ビルや建物などのメンテナンスや保守。日々工数をかけてメンテナンスや保守をする事で、使用できる寿命が長くなります。
この「メンテナンス」や「保守」をやらないとどうなるでしょうか。ソフトウェアを例にあげると、ソフトウェアが陳腐化したり、時代遅れになったり、新しいセキュリティ対策をしなかったことによりウィルスにやられてしまったりします。
それでは、これを購買に置き換えて考えてみましょう。
最初に正しい購買プロセスを経て「適正価格」を取得しても以降放置していると、より安い価格の取得機会や同価格で好条件(サービスレベル)に変更できる機会をみすみす逃してしまうのです。これは市場に比した「適正価格」を維持できていない状態であるといえるでしょう。
契約更新時(自動含む)も、新規契約時と同様に正しい購買プロセスを経る必要があるのです。
特に間接材においては売り手と買い手に情報格差があり、一度コスト削減が実現できたとしても、情報の格差を常に埋め続ける努力をしないと「適正価格」は維持できないのです。
ソフトウェアやシステムにメンテナンスや保守が必要なように、「適正価格」を維持するためには「価格のメンテナンス・保守」といった継続的な手段を講じる必要があるのです。
購買にもメンテナンス・保守を!
「適正価格」のメンテナンス・保守とは、適正価格と適正価格に見合ったサービスレベルを維持できているかの情報格差を常に埋め続ける事です。そして“価格”・“サービスレベル”・“品質に対する価格”を確認し続け、チェックし続ける事なのです。もちろん“仕様”や“売り手企業”のメンテナンス・保守も必要です。
この間接材の「適正価格」のメンテナンスや保守は、購買している「もの」や「サービス」の特性によって、頻度や間隔が決まります。例えば、業務委託契約のように1年おきに契約更新するものは、定期的に実施するだけで十分でしょう。
このように、一度適正価格化ができたとしたとしても、継続的な「メンテナンス・保守」を怠ると、すぐに元に戻ってしまいます。
ダイエット後のリバウンドと同じような事が、購買の価格についても起こるということをご理解いただけたでしょうか?
谷口健太郎 著 「間接材購買戦略-会社のコストを利益に変える」東洋経済新報社 を要約
谷口健太郎 著書
「リバースオークション戦略」東洋経済新報社
「間接材購買戦略 〜会社のコストを利益に変える〜」東洋経済新報社この記事が「参考になった!」と思ったら、facebookまたはTwitterでぜひ
“シェア”をお願いします。
間接経費のコスト削減‟お役立ち”コラム集
関連ページ
事業・サービス紹介
DeeCorpのメソッド
間接経費のコスト削減支援で20年間、ディーコープがご支援して参りました大手企業を中心とした3,177社以上の買い手企業様の”間接経費(間接材・サービス)のコスト削減”を支援してくることで得られた購買ノウハウや、考え方を体系化した“メソッド8種類”をご紹介します。
>>続きを読む事業・サービス紹介
間接経費のコスト適正化支援
ディーコープが間接経費のコスト削減の専業企業として培った情報やノウハウを活用し、間接経費(間接材・サービス)の購買におけるコスト削減と最適化ができる様にサポートしていきます。 ディーコープ独自のアウトソーシングという仕組と立ち位置で、適正な市場価格を導きだします。
>>続きを読む事業・サービス紹介
見積取得支援システム”見積@Dee”
相見積取得支援サービス”見積@Dee”を用いることで、ディーコープが蓄積した間接経費(間接材・サービス)に関するノウハウとコンサルタントによるサポートを得れます。またディーコープが長年の活動で取得したサプライヤリストを活用いただけます。
>>続きを読む