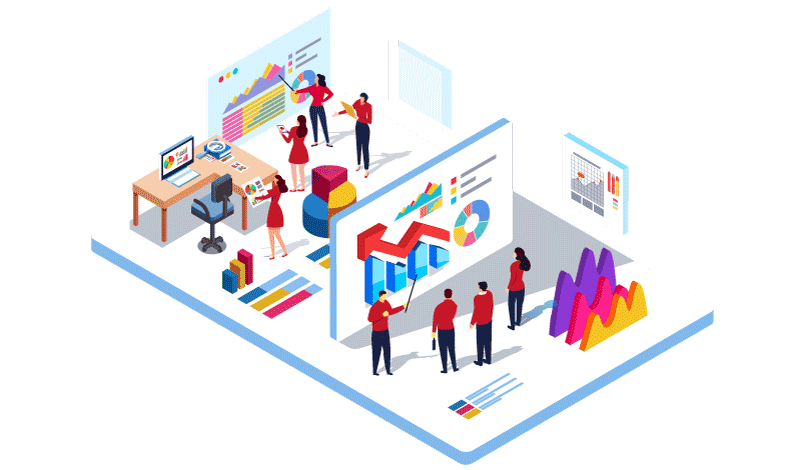「現場が動けば、経営が変わる」購買DXが求める管理職の役割とは?
朝夕に秋の気配を感じる季節となりました。購買部門の皆さまにおかれましては、年度後半に向けた調達計画の最適化が求められるタイミングではないでしょうか。
尚、以降の内容は2025年8月実施の弊社独自調査結果に基づく考察となります。
今回は、購買部門の管理職として日々業務改善に取り組まれる皆さまに向けて、 「購買DX」の本質と、管理職だからこそ担える役割についてお伝えします。
ポイント:購買部門の“現場”が変われば、経営も変わる
最新の調査では、大手企業の73.3%が購買管理システムを導入済みであり、すでに「購買DX」は全社的な改革の一環として位置づけられています。
中でも「間接材購買」は、見落とされがちなコスト領域でありながら、手作業や紙ベースの運用が温存されているケースが多く、変革のインパクトが大きい領域です。
理由:現場の管理職が“変革の起点”になれる理由
調査結果によれば、購買業務における主な課題は以下の通りです:
- 購買プロセスの非効率性(27.7%)
- コスト管理の不明確さ(19.3%)
- データ分析の活用不足(15.7%)
これらは、現場を熟知する管理職の視点と提言があってこそ改善が進む領域でもあります。また、導入の障壁として挙げられる「業務との適合性」や「社内理解不足」も、現場と経営の橋渡しができるポジションだからこそ克服できる課題です。

例えば:購買DXがもたらす“成果”とは?
導入済みの企業では、次のような成果が実際に現れています:
- 業務効率化(55.4%)
- コスト削減(31.3%)
- データ可視化・経営レポーティングの迅速化(27.7%)
特に「購買業務の非効率性」が課題とされた企業の87%が、業務効率化の実現に成功しているというデータは、説得力のある成果指標といえるでしょう。
ポイント:経営層に「自社の現状と課題」を届けるのも、管理職の役割
約6割の企業がシステム導入の必要性を感じているにもかかわらず、実際に情報収集を行っている企業はわずか26.5%にとどまります。
「現場ではこんな課題がある」「こうすれば改善できる」――それを、経営層に届けられるのは現場を理解する管理職であるAさんのような方に他なりません。
だからこそ、“購買DX”は経営トップの意思決定事項であり、そこに提言できるK管理職の存在が極めて重要なのです。